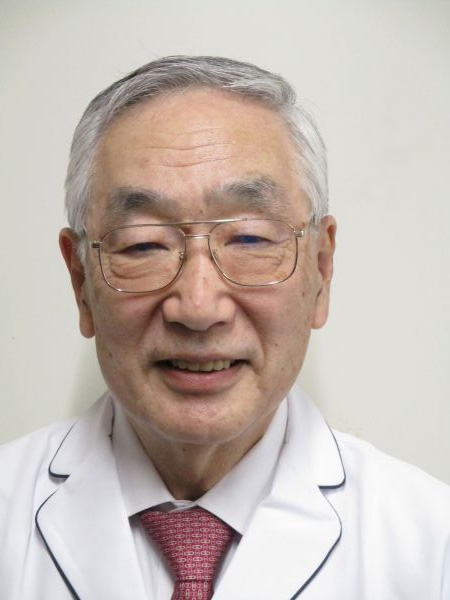
院長 德橋 泰明
北本病院(正式名称:医療法人財団 博翔会 桃泉園北本病院)は、従来、リハビリテーションや慢性期医療に特化した病院でした。
病院の理念は、昭和56年に病院がスタートして以来「私たちは地域の皆様が信頼し愛する病院を目指します」です。
そして具体的には、「地域と連携しながら患者さんが元気に自宅へ帰れるよう支援する」ことでした。
近年は、社会の高齢化を反映して、より質の高い医療サービススの提供が必要になりました。
そのため、内科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、循環器外科、消化器科内科、消化器外科、泌尿器科、人工透析内科、血管外科など幅広い診療科による医療を目指しています。
新医療技術や最新のMRIなど新しい機器設備を整え、脊椎手術や人工透析専門病棟、下肢静脈瘤の治療、脳ドックや骨粗鬆症診断治療、そして質の高いリハビリテーションなど専門性の高い、特化した医療サービスも提供できるようになりました。
このような質の高い医療サービスを提供する上で何よりも大事にしていることは、スタッフ一同が、一人ひとりの患者さんと同じ目線で向き合い、丁寧な対応を積み重ねることだと考えています。
地域との連携も、病院内だけでなく、通所リハビリテーション、訪問診療介護などより大きな広がりとより緊密な連携が必要になりました。
北本病院は地域を支える重要な拠点の一つであり、このような社会の必要性に対し、私たちから地域へ信頼の輪がさらに繋がっていくよう、病院の体制をよりレベルアップし、スタッフ一丸となって邁進してまいります。
